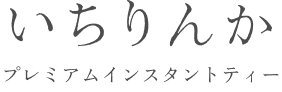日本茶も美術品も日常の中で愉しめてこそ
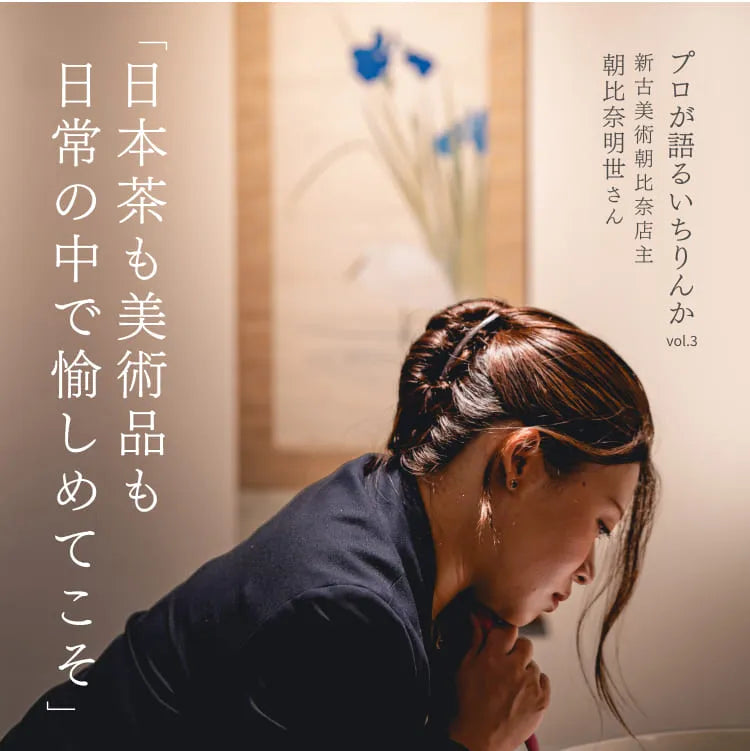
日本茶も美術品も日常の中で愉しめてこそ
長年にわたり日本文化の中心地として歴史と伝統を支えてきた京都。それだけに、日本文化に向ける目が厳しくなるのも必然の流れなのかもしれません。特に茶道とも縁の深い古美術の世界では、お客様へのお茶出しは非常に重視されているそうです。
そんな京都で古美術ギャラリーを営む朝比奈明世さんに、お茶出しやギフト選びで大事にされていること、そしてご自身のリラックスタイムについてお伺いしました。(2025年6月10日インタビュー実施)
---
お客様にも喜ばれている「いちりんか」
古美術といわれても馴染みのない方が多いでしょうが、掛軸や屏風、茶道具などを想像していただくと分かりやすいかと思います。例えば私のギャラリーでは、江戸時代に描かれた絵画や書、漆地に金で美しい文様を描いた蒔絵のお道具などを中心に多くの作品を展示・販売しています。
そのため、お客様が作品を見る時も真剣そのもの。非常に集中してご覧になっています。
そんなお客様に少しリラックスしていただくため、おもてなしの気持ちを込めてお茶をお出ししています。「いちりんか」は色合いも美しく、またお茶の持つ豊かな香りと味が楽しめるので、お客様にも自信をもってお出しできます。
京都や古美術の世界でお茶は非常に重要
私のギャラリーは京都にあるのですが、京都は茶文化が盛んな土地です。お茶の生産地として名高い宇治や、お茶の総本山の大徳寺、茶道の主要流派の三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)の本拠地もあるので、茶道の心得がある人も少なくありません。
また、古美術店は茶道で使われる茶道具や掛物を扱うことも多く、「古美術店」と「お茶」は切っても切れない関係です。
そのため、古美術店は総じてお茶に非常に気を遣っていると思います。
例えば、あるお店は、お客様がいらっしゃるごとにお抹茶を点ててお出ししています。また、私が修行していた店では、来廊されたら緑茶、お菓子を召し上がられた後はほうじ茶、この先生には洋菓子と紅茶といった具合に、タイミングや相手に応じて様々なお茶を出していました。
このようにお茶について高い水準を求められる環境だからこそ、私もギャラリーでのお茶出しは非常に重要だと考えています。お茶の品質はもちろんのこと、出すタイミング、種類、温度、器に至るまで気を抜けません。
冷たいお茶もすぐに出せるのが心強い

京都の夏は、本当に蒸すような暑さです。そのため夏にお越しになったお客様には素早く冷たいお茶を出したいですし、作品をじっくりご覧になった後なら冷房で身体も冷えるでしょうから、温かいお茶も必要です。
そんな時、「いちりんか」ならお湯やお水に溶かすだけで作れるので、お客様をお待たせしません。すぐにお客様との会話にも戻れるので、私にとっては非常に心強い存在です。
ギフトとしても使いやすい
古美術品は、長年に渡って人から人へと受け継がれてきたからこそ、今この世界に存在しています。だからこそ、私にとってお客様は、単に「作品を買ってくださる人」ではありません。「この作品を守り、後世に伝えてくれる人」だと思っています。
そんな想いもあり、私は作品を納品する時、お手紙や資料に添えてちょっとした贈り物をお送りすることが多いのですが、「いちりんか」はギフトとしても非常に重宝しています。
日持ちも好みも心配しなくて良い「万能ギフト」

贈り物選びは、相手の方のことを考える楽しさがあると同時に、「失敗できない」と頭を悩ませることも多いですよね。気持ちが伝わるセンスの良いものをお送りしたいですし、賞味期限が短いものや利用に手間がかかるものは避けたいものです。
その点、「いちりんか」なら五感で楽しんでいただけますし、日持ちもするので賞味期限の心配もありません。
急須を持っていないお一人暮らしの方からお茶が好きな方まで、年齢や性別を問わずどんな方にも喜んでいただける味と便利さを備えていると思います。まさに「ギフトとして万能」です。
作品と一緒にお送りする時はもちろん、手渡しの際も軽くてかさばらないので、ちょっとした手土産にも便利です。
初めはギフトとして貰った「いちりんか」
実は、私が「いちりんか」に初めて出会ったのも、お客様から差し入れとして頂いたのがきっかけでした。香りが鼻に抜ける感覚、そして急須で淹れたお茶の味の「良い部分のみ」が口に広がる感覚があり、とても新鮮に感じたのを今でも覚えています。
お茶に詳しい方に聞いたところ、茶葉から入れる一般的なお茶の場合、熱湯で淹れたお茶は「旨味」を感じにくい一方、ぬるめのお湯だと香りが立ちにくいのだそうです。旨味と香りの両方を同時に感じる体験が初めてだったからこそ、非常に驚いたのかもしれません。
仕事終わりのリラックスタイムに

個人的に、一番好きな味は「香りうっとり」です。甘くて上品な香りに癒されながら、温かいお茶をゆっくりと時間をかけて飲んでいます。また「香りふくよか」はお抹茶を頂いたような感覚で、これもまた一口、また一口とお酒のように少しずつ頂いています。
古美術商というと「鑑定人」のイメージが強いでしょうが、実は、日常の大部分を占める仕事は「仕入れ」です。毎日のように全国各地で開催される「交換会(業者オークション)」へ出向き、目利きをし、欲しい品を競り合います。長時間にわたる交換会で疲れた時などは「いちりんか」の香りと美味しさに癒されています。
疲れ切っている時に、お湯を注ぐだけで飲める手軽さは嬉しいですね。
「今の時代」に合っていることが大事
これは私の個人的な印象なのですが、サントリーさんは「今の時代」「今の人々の生活」をよく見て、それを踏まえて商品や文化を作っている会社という印象があります。
仕事柄、サントリーと聞くとサントリー美術館を思い出すのですが、展覧会の企画を見ても、日本美術という「古臭くてつまらない」と思われがちなものを、今の人が興味を抱きやすく楽しみやすい切口で紹介してくれています。
そういう会社だからこそ、本格的な日本茶の味わいを備えながらも、忙しい毎日の中で手軽に飲める「いちりんか」という商品を生み出せたのではないでしょうか。そして、そんな姿勢に、私はとても共感をしています。
毎日の生活で楽しめてこそ価値がある

私が自分のギャラリーで扱う作品を決める時に大事にしているポイントの一つが、「現代の一般的な居住空間に美しく納まる作品なのか」という点です。
お客様のご自宅に飾られた時に「あれ、何か違う」「お店では素敵に見えたのに」と思われてしまったら、お客様にも作品にも申し訳ないです。だからこそ、自宅に飾った時の姿を想像しやすいよう、ギャラリーのインテリアも一般的な白壁と床の間風の壁の二面を用意しています。
お茶も同じだと思っています。どんなに良い茶葉であっても、自分でお茶を淹れた時に美味しく飲めなければ、意味がないですよね。でも美味しいお茶を淹れるには、手間暇や知識、さらにはちょっとしたセンスも求められます。しかも茶葉は鮮度が重要なのですが、お茶は一袋の量も多く、「余らせているうちに風味が落ちてしまった」という経験がある人も多いのではないでしょうか。
私自身も、有名なブランドのお茶を現地で飲み、その時は感動したので茶葉を買って帰ったけれど、帰宅後にお茶を淹れたら「何かが違う」と感じた経験があります。
急須と湯飲みをお湯で温め、温度調節をしたお湯を用意し、ゆっくりお茶を抽出する。さらに飲み終わったら急須や湯飲みを洗う。忙しい日々の中で、これだけの時間と余裕を確保するのは非常に難しいです。
でも、日本茶の味や香りを愉しみ、それを通じて心を整える時間は、昔よりも重要性を増しているように感じます。「いちりんか」は、日本人が長年受け継いできた「一杯のお茶をゆっくり頂く」という文化を、現代の生活にもたらしてくれる商品なのではないでしょうか。
---

朝比奈明世
京都の八坂神社隣にある「新古美術 朝比奈」の店主。大学時代は文化財学の分野で美術史、考古学、保存科学、史料学を学び、学芸員資格も取得。卒業後は京都の老舗ギャラリーにて7年の修行後、独立。
自身の専門分野である書画・墨蹟を軸に、日々、第一線で全国の美術オークション・交換会に出向き仕入れを行う。深い見識と空間を提案するセンスで、日本人はもちろんのこと海外にも顧客を持つ。https://www.asahina-art.com/
ご購入はこちらから↓